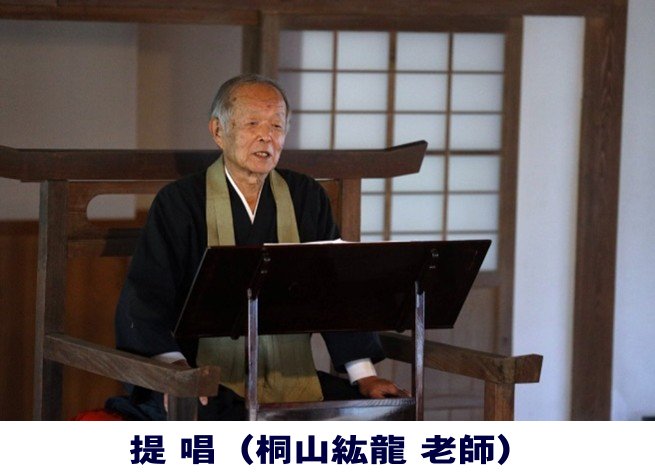はじめに
紅葉もきれいで快晴の秋空の下、今年もまた正受庵での坐禅会が開催できました。
釈迦牟尼会を取り巻く情勢がいろいろと変化する中で、本会主催の坐禅会が継続できたことは感慨深いことです。
この意義を多くの皆さんと共有するためにも、ここに報告書をしたためます。
正受庵仕様の差定等は例年並みで大きな違いはありませんが、これに従って順に記します。
|

|
1.坐禅・独参
昨年は、本堂屋根の改修に伴い坐禅堂が作業場等となったために使えず、坐禅を庫裏で行いましたが、今年は坐禅堂で行うことができました。
堂内は参加者の静かな熱気にあふれていました。独参は山本・桐山両老師が二部屋に分かれて同時に進め、併せて内参も行って頂きました。内参では東京道場の参禅者が桐山老師の隠寮に、長野禅会の参禅者が山本老師の隠寮に入るという積極的な姿も見られ、普段はなかなかできない貴重な時空となりました。
|
2.提唱1:飯島老師【世尊拈花】
午前中に行われた飯島老師のご提唱「世尊拈花(無門関第6則)」の概要を記します。
世尊拈花の則は、世尊が成道し、悟りの中身である法を摩訶迦葉に伝えた、という内容である。この話は史実ではなさそうだが、法を伝えるとはどういう事実であるかを端的に物語っているので、素晴らしくよくできている。

釈尊はインドの霊鷲山で法を説いた。花を執って多くの衆に示したが、皆ポカーンと押し黙っていた。皆は釈尊が花を掲げ持った後に何か話をするだろうと思ったが、釈尊は花を示すだけであった。
この時、摩訶迦葉だけがほほ笑んだ。これに対して世尊が「吾に正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)、涅槃(さとり)の妙(たえ)なる心、実相無相、微妙(すばらし)き法門有り、文字を立てず、教の外(ほか)で別に伝える、摩訶迦葉(まかかしょう)に付嘱(あた)う」と言った。
法の伝授が無言のうち行われた、つまり法を伝えるには言葉が不要であることを端的に示している公案と言える。摩訶迦葉と釈尊が同じ心になってニッコリしたのである。
ところで、釈尊が言うところの正法とはどういう事実かというと正しくない法などは微塵もなく、全てが正法であるということである。二つあったら仏法ではない。
目を開ければ見たままにあるがままに知覚する、あるがままにある、これが正法であり正受である。正法に生きた人が正受老人であり、正法が現前している場所が正受庵である。
見たまま聞いたままに受け取ることを正法眼と言い、蔵とは、それがすべてであるということである。これが正法眼蔵の意味である。仏様だけでなく私たちの肉眼が正法眼蔵である。これが涅槃妙心(さとりの妙なる心)であり、実相無相である。見ているものは、そのままであらゆる姿・形(実相)を超えている、姿・形はあるままでしかもない(無相)。
|
「パチン」(両手で叩く音)と鳴れば耳はそのまま受け取る(正受)が、頭を使って概念にしたとたんに真実から離れる。概念化すると「パチン」という真実そのものから離れる。どういうふうに離れるかというと、「飯島が手をたたいた」という説明に堕してしまう。事実についての「説明」と「事実」とは全く別のものであるということが理解できなければ、禅は理解できない。
「ガアー!」(カラスの鳴き声)も概念化すると真実から離れる。ただ「ガアー!」である。「カラスが鳴いた」と言語化するよりも、「カラスは鳴かなかった」と言語化することを禅者は好む。事実を事実のままに捕らえる為には、「カラスは鳴かなかった」という言説のほうが常識的理解を砕くのに適しているからである。事実は、カラスは鳴くのでもなく、鳴かないのでもない。ただ「ガアー!」である。
釈尊はここでは無言であったが、釈尊も歴代の祖師方もやむ無く文字・言葉を使うが、文字(言葉の意味するところ)に事実はない。これが不立文字であり、教の外(ほか)で別に伝えるということである。
釈尊は摩訶迦葉に何を伝えたかったのか。釈尊成道(見明星悟道)、明けの明星を見たとき、三昧が破れ「我と大地有情が共に成道す」と言葉を発した。釈尊が悟ってみたら、生とし生けるもの全てが悟り尽くしていたという事実に気づいた。
ここで無門が言う。世尊は勝手な事を言っている、大衆は皆黙っていたというが「黙然」で立派、それで十分じゃないか、なんの不足もないではないか。
もし大衆が皆笑ったら、正法眼蔵をどのように伝えただろうか、逆にもし迦葉が笑わなかったら、正法眼蔵を伝えられなかったのではないか。
もし正法眼蔵に伝授ありと言えば、世尊は大衆をたぶらかしたことになる、伝授なしと言えばどうして摩訶迦葉だけを認めたのか。
不伝の伝、伝えずして伝えるということ。「闇の夜に鳴かぬカラスの声きけば、生まれぬ先の父ぞ恋しき」。この鳴かぬカラスの声を聴くことができれば何もかもがはっきりするし、釈尊と同じ心を味わうことができる。
花を掲げることが丸出しの事実であり、この意味を頭で探れば釈尊の心から離れてしまう。摩訶迦葉がにっこり、集まった人も神もこの「にっこり」、には手もつけられない、摩訶迦葉の絶対的な笑いである。この一つ一つの端的が正法眼蔵の中身である。実にこの公案には、深い意味での摩訶迦葉に伝えないで伝えるという伝え方(不伝の伝)の端的が示されている。
今日の独参の姿がそのまま霊鷲山の出来事である。皆さん自らが探究して答えを出す事がそのまま霊鷲山の出来事と同じである。
釈尊から歴代の祖師方、そして正受老人・白隠へ、更に山本老師・桐山老師へと脈々と伝わってきている正法の中に、皆さんがまるごと生かされていることを自覚し、この正法を自ら獲得すべく精進して欲しい、と激励されながらご提唱を結ばれました。
|
3.提唱2:桐山老師【禅を生きるⅡ】
午後に行われた桐山老師のご提唱の概要を記します。
昨年の正受庵の提唱で量子論を話そうとしたが、唯識で終わってしまった。今年、もし途中で終わったとしても、この提唱用資料を読んで頂ければ、私の意図していることが分かる。資料で重要なことを話す。前著作「禅を生きる~自覚への道~」の発端は、光龍老師が著書「在家禅の巨匠」で示した禅の本質にある。本著は禅を尽くしているので、これを座右の銘として頂きたい。とりわけ「西洋の科学文明を本物にする禅の実力」(光龍老師)は、土居さんもご著書「世界のための日本の心」で指摘するように、日本の心を表している。これらの事柄を追究した結果を「禅を生きるⅡ」で書いてみたい。目次や構想だけは既にできているが、気づいた事があれば教えて欲しい。
現代の我々の生活は、飛行機・車・電気器具・スマフォなど科学のおかげで成立している。科学の最先端とも言える量子論やビッグデータを駆使しての生成AI及びチャットGTPの登場は、利便性もあるが今後の発展の仕方次第では空恐ろしい危険性もある。長野禅会でも多くの話し合いをしたが、ICもAIも数学的・情報処理的技術であり、結局は人間の使い方に問題があるという結論らしきものが見えてきた。良い人間が使えば好結果が得られるが、悪い人間が自国最優先に使えば、必ず争奪戦や分捕り合戦などが起こる、という具合である。
ところで、唯識思想には「唯識無境」ということがあり、この宇宙は人間も含め全部(山・川・草木等)が意識であり、この考えは禅の背景に脈々と受け継がれている。山本老師は「現象そのものが心であり、私がここに居て物が向こうにあるのではない」と言われたが、これが唯識無境である。また、経机を「トントントン」と叩き、「これはこれでいいでしょ、完全無欠です。キリストもマホメットも世界中の人が直ちに分かる」と言われたが、これが唯識の基本である。
これまでにも話してきたが、全ての物を細かく分けていくと分子・原子に、更に量子論の段階では素粒子となる。山・川・人間などすべての物は素粒子の集まりという事になるが、不思議なことに10のマイナス何乗という極微小な素粒子では、粒子でもあり波でもあるという相反した現象が起こる。
|
男と女は全く違いながら補い合って生きているように、善・悪や衆生・仏も全く違うのに依存し支え合って生きている。これをデンマークの物理学者ニールス・ボーアは「相補性の原理」とよんだ。
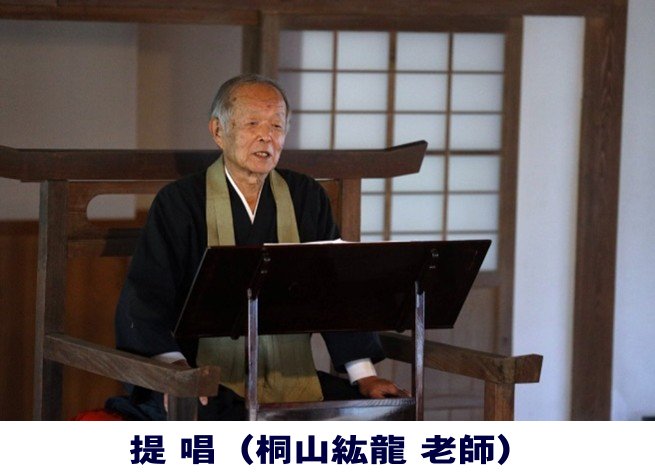
ニールス・ボーアは日本にも来て日本文化や東洋思想に着目している。これらはプラス・マイナスや賛成・反対という相反する物事をそのまま捉えること、つまり高い所から俯瞰して物事を調和的に捉える仕方であり、日本文化の特性である。西洋科学文明と禅とで言えば、科学は二元論だが禅は一元論で、善・悪を超えたところから善悪を判断する。また、イタリアの理論物理学者カルロ・ロヴェッリは龍樹の「中論」を研究し「空」の思想から「世界は関係で出来ている」と、やはり東洋思想に活路を見出している。この様に、東洋思想や禅にはすごい力がある。禅を修する皆さんは、是非この事を弘めて頂きたい。世界では争いや分捕り合戦が絶えないが、東洋思想や日本文化とりわけ禅には、この争奪をなくす力がある。これは日本の特権で日本にしかできない事である、と力説された。
最後に、ご提唱を総体的に理解する一助にと、我々の心や無心の構造とこの生成発展過程とを、大円鏡智の図を用いて視覚的にも分かり易く説かれ、ご提唱の座を降りられた。
|
4.ありがとう禅
全員で堂内をゆっくりと経行しながら、桐山老師の木魚を叩くリズムに合わせて繰り返し「ありがとう」を唱えました。長野禅会では毎回実施していることですが、これまでの正受庵の坐禅会でも採り入れて来ましたので、スムーズに行われました。経行は歩く坐禅と言われますが、加えて「ありがとう」を高唱することで三昧の一層の深まりが期待されます。坐禅のワークショップ(参加型体験)にもなりますから、経験者にとっても新たに坐禅を始めようとする方にとっても、手応えの一つになるかも知れません。
|
|
5.墓参
釈迦牟尼会の先師方の墓参は不二道場でも欠かさずに実施されていますが、更に法系を遡る正受老人の墓参は、気持ちを新たなものにさせてくれます。無難・正受老人・白隠のそれぞれの尽力や遺徳を併せて思い起こせるからです。坐禅をする場所はどこでもよく、これを問うことはありませんが、墓参はやはり正受庵境内で行うことに意義があるのだと思います。正受老人の漢詩に「・・・我が心を知りたければ、庭前の松の木を見よ・・・」(意訳)があります。現在、墓を抱くようにあった松の木はありませんが、周辺の木々がおもかげを偲ばせてくれます。
|

|
6.茶礼
土居さんの巧みな司会進行により、車座での茶礼という和やかな雰囲気ながらも、深い意見交換が行われました。主な内容を略記します。一つ目は、ここ正受庵での坐禅会ではいつもと違った雰囲気の中で自分の意志以上の力で坐る事ができること、また感性が高まるのか、般若心経も坐禅和讃も唱えているエネルギーを感じる事ができること、など場の力や聖地に関係した話が出された。土居さんは、正受庵が聖地であるように、不二道場も聖地として残さなければならないと力説された。二つ目は、桐山老師のご提唱に関わることで、AIは慈悲の心をもてるのか?という疑問に対し、AIに心を入れる、論理・知識に頼らないものをどのように入れていくか、この座でのこの話をAIに聞かせれば、AIがまとめてくれるかも知れない。AIの出現で人間の悩みはなくなるのか?、否、なくならない、これを使う人間の人格や使い方の問題である、相補性に関しては、飯島老師から、いい加減な話と緻密な話を相反するものとすれば、私(飯島老師)の提唱を桐山老師に評価し位置付けて頂いたことは、内容が三角(いい加減)から楕円(緻密)になったので相補性の原理が働いたことになる、とこの原理に対し謙遜しつつ自らの事例で肉付けをされた。また、ありがとう禅についても、飯島老師の地元藤沢市の踊り念仏と重ね、無我無心を目指す点では同じであると評価された。
山本老師は、ありがとう禅は摩訶般若波羅蜜多である。あらゆる生命の根底には慈心があり、ありがとう=摩訶般若波羅蜜多がある。飯島老師は拈花微笑の話をされたが、釈尊から摩訶迦葉に、更に正受老人から白隠に法が伝わるという仏法の伝統があるから、我々は互いに修行ができる。例えば、無字の公案では私が無字を拈提していると思っているが、実は無字が拈提しているのである。修行は大変だが、諦めないでやっていれば必ず自ずと自分に返ってくる、到達し開ける。私(山本老師)も学人で途中である、とこの上ない励ましを頂き、総講評とされた。
|
7.慰労懇親会・等
三人の老師方を囲んでの慰労懇親会は、帰りの電車等の都合もあり長時間はできませんでしたが、「飲むほどに、酔うほどに」参加者相互に自由で楽しい意見交換ができました。また、老師方の現在のお立場や心境から、ほろ酔いの中にも緊張感・行く末の希望や展望なども語られ、有意義なものになりました。なお、三人の老師方はお泊りにもなられましたので、更に厳しくも楽しい三賢人懇談がなされたことと拝察いたします。この懇談内容は、いずれ何らかの形で釈迦牟尼会の今後の運営等に反映されることと思われます。
|
<おわりに>
三老師の揃い踏みという形で開催できた今回の坐禅会は、本会の歴史を画するものになるだろうと思います。この印象は、両老師のご提唱内容からも、また茶礼での意見内容からも少なからず感じられます。今回語られた「聖地」や「相補性の原理」などの意味が、諸氏がそれぞれに表明された内容以上の複数の意義を孕んでいますので、関係者の皆様のご尽力に感謝しつつ、注視し協力し合っていきたいと思います。ありがとうございました。
|