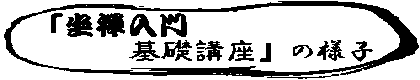
|
長野禅会では、より多くの方に坐禅に親しんで頂きたいと、坐禅基礎講座を計画し実施しました。 1.講座の開設まで (1)開設のねらい ①より多くの一般市民の方々に坐禅への門戸を開き、親しんで頂く。 ②坐禅の呼吸法と姿勢を経験することにより、心の安心を得たりして頂く。 ③坐禅のよさを知って頂いた方には、長野禅会等で継続して実施して頂きたい。 (2)開設への手順 ①長野禅会が借用している会場のサンライフ長野に、講座の主催者になって頂く。 ②主催者の側から、参加者募集のチラシや市の広報で、広告・案内を出して頂く。 ③応募受付や参加費(1回当たり300円)徴収は、主催者にして頂く。 ④講座の内容や運営は、実質的には長野禅会が担う。 2.講座の内容 (1)第1回目:坐禅の作法を中心に、実習しながら解説を行う (2)第2回目:坐禅の実習 坐禅の姿勢と呼吸法や、禅と健康について話す (3)第3回目:坐禅の実習 禅と生活等について話す 3.第1回目講座の実際 (1)8月26日 参加者19名(一般=16、桐山講師・鈴木助士・峰村助士) (2)タイムスケジュール ①12:00 打ち合わせ・会場設定(講師と助士で準備品をセットする)、準備品(座布団23・坐禅用座布団30・受付テーブル1・受付名簿・経典・反省記入用紙・筆記用具・他) ②12:30 受付開始(名簿へ○印をつけ、隣接の控え室で支度をして開講を待つ) ③13:00 開講(主催者は講師助士紹介と会場使用規定説明等、以下禅会で進行) ④13:10 オリエンテーション(桐山主宰が、足の組方・姿勢・呼吸法・心構え・入退場法等について、助士の見本もみせながら丁寧に説明をする) ⑤13:40 実習Ⅰ(仏足頂礼して入場・合掌歩行・安単に坐る・般若心経と三綱領の読経読誦・20分間の坐禅) ⑥14:05 休憩(講師等への質問も受け付ける) ⑦14:15 実習Ⅱ(25分間の坐禅・四弘誓願の読誦) ⑧14:50 閉講(次回の予告をし、参加者が感想や反省の記入した後、解散する) (3)基礎講座のキーワード 先ず、桐山主宰から参加者へ、参加して頂いたお礼の挨拶があり、次いで、初めて坐禅を実際に行う人のために、以下のことを丁寧に説明した。 ①摂心の三要:坐禅を行うに当たって、三つの要(・社交的な頭を使わない・よそ見をしない・無駄口をしない)を守ることが大事である。 ②坐禅の基本:◎調身(足・背骨・顎・目について)・◎調息(欠気一息・自然でゆっくりとした呼吸・決して無理をしない・呼気と吸気の転換点を丸く柔らかく・数息観や随息観に従って)◎調心(呼吸は人間の意志を超えた命の働きで根本知(仏心)・呼吸に全てをうちまかす・妄想や念を相手にもせず邪魔にもせず継がないようにする・即今ただいまの自分に徹する)ことが、体と心を整える上での基本である。 ③読経:読経は、数息観と全く同じで、恥ずかしがらずに朗々と読経できるようになると、坐禅が深まっていく。本来の自分やありのままの自分が働き出し、自信をもった生活ができるようになる、ので大切なことである。 (4)参加者の主な感想や質問 ①1回坐った後の質問 質問:説明通りの呼吸をしていたら、苦しくなったが、どうすればよいか。呼吸は鼻でやるのか、口でやるのか。 答え:呼吸は無理をせず、自然で楽にできる形でゆっくりとやればよい。呼吸は出来れば鼻から吸って鼻から出すとよい。口でやると口の中が乾いてしまう。 その他にも、記載された質問があったが、時間の関係で、第2回目に回答をした。  ②2回坐った後の感想
②2回坐った後の感想○坐禅を基本から教えてもらってよかった ○姿勢を正しくしたせいか、胃の痛みがなくなった ○以前から坐禅に興味があり、参加できてよかった、体をまっすぐにして、腰骨を立てたらとても気持ちよかった ○更年期で体調不良となり、市販本で自己流の呼吸法でやっていた、警策は少々痛かったが、気持ちよかった、次の坐禅体操を楽しみにしている、大勢で坐るといいものだ、あっという間だった、長い呼吸は続かないが、今後ゆっくり慣れていきたい ○20分の坐禅はできるか、不安があったが、やってみると短く感じた ●呼吸のやり方が全く分からなかった ●呼吸を意識することは、なかなか難しい、日々当たり前にやっている呼吸だが、改めて意識することは大変である ●雑念ばかり浮かび、全く集中できなかった ●数を数えるが、途中から違うことを考えていることの連続だった ●足がしびれて、坐っていることがとても大変だった ●坐禅のときの目のあり方、集中してみていると体が硬くなるように感じる 4.第2回目講座の実際 (1)9月2日 参加者19名(一般=16、桐山講師・鈴木助士・田中助士) (2)タイムスケジュール(第1回とほぼ同じ、2回の坐禅に加え質疑への回答) (3)第1回目及び第2回目での質問に対する回答(桐山講師) ①Q:長野禅会はどこで行っているのか? A:ここサンライフ長野で、原則的には毎月第1日曜日の午後1時半から5時まで。変更することもあるので、長野禅会のホームページ等で確認して下さい。 ②Q:呼吸や姿勢が正しく出来ないときは、どうすればよいか? A:正しい呼吸は無理のない自分の呼吸ができるようになること。ゆっくりした呼吸を心掛けること。7~8秒位かけて息を吐き、3~5秒位かけて息を吸うと気持ちが楽々として安定する。しかし、無理をして息を長くしようとしないで、少しずつ調子を合わせるように意識して呼吸するとよい。ゆったりした呼吸は自律神経を安定させるし、血行もよくする。自分の姿勢が悪いと自分で分かれば直せばよい。自分で分からないときは、人に見てもらうのがよい。先ず、腰や背骨をしっかりと立ててみて、どこにも無理がかからない自然の姿勢になること。病気や体調不良は、姿勢が悪いことで起こることもある。 ③Q:家で坐禅をする場合、いつ、どのくらいやればよいのか? A:朝起きたときや寝る前に30~40分できればよい。人によって環境や条件が違うから、初めから無理をせず、できる範囲で続けるのがよい。朝、坐禅と読経をすると一日の活力が生まれる。 ④Q:妄想がでてきたり、途中から違うことを考えたりする時、どうすればよいのか? A:考えることは当たり前で、いわゆる妄想といわれるが、我々が生きているから出てくるので、日常では必要なこともある。しかし、考えがどんどん進んで、それにとらわれて肝心なことが前進しなくなると、それが妄想である。坐禅はそうならないための訓練である。いろいろな思いがでてきたら、それについて回らない、相手にしないでそのままにしておく、というのがこつである。数息観の途中で違うことを考えた、と気付いたら、「ひとーつー」に戻ること。その繰り返しをどこまでも続けること、それがとても大切なところ。 ⑤Q:坐禅のときの目はどのようにすればよいか? A:坐禅中の目は常に開けるが、凝視して見つめることではなく、前方に視線を軽く落とす程度で、全体がぼんやり視野に入っている感じである。初めは、どうしても見えるものが気になるが、そのままにして呼吸に集中するようにすると、いつの間にか、見ていながら見ていないという状態になる。聞いていながら聞いていない、つまり、とらわれない練習である。 ⑥Q:警策は、なぜ坐禅の始まった直後だけなのか?途中での「喝!」はないのか? A:坐禅の途中での「喝」の警策もあるが、今日の皆さんの場合は必要なかった。 (4)参加者の主な感想 ○リラックスできてよかった、坐禅体操が楽しかった ○頭に浮かんでくることに、とらわれないことが大切だ、ということが分かった ○気がつくと、違うことを考えていたが、終わった後は、落ち着いた豊かな気分だ ○合掌すると、思わず「南無・・・」とでてしまう ○エアコンの冷気に腕は寒かったが、おなか(内臓)はぽかぽかだった ○足はしびれたが、気持ちがよかった、会場に入ったとき、家であった雑念がスーッとした感じがし、すっきりした ●2度目の坐禅は、眠気との闘いであった、瞬きと呼吸が合わず、呼吸のリズムが狂ってしまったのが、今日の課題であった ●今日はあまり集中できず、目がショボショボし、呼吸も姿勢もよくなかった 5.第3回目講座の実際 (1)9月9日 参加者18名(一般=15、桐山講師・鈴木助士・峰村助士) (2)タイムスケジュール(第1・2回目と同様に2回の坐禅に加え、30分の茶礼あり) (3)基礎講座を終えるにあたり(峰村助士) 受講された方々が、この経験を今後に生かして頂けるように、次のような講話を行った。 ①凸レンズの譬え(坐禅では、体も心もどっしりと坐りたいが、どうしても心は乱れ勝ちとなる。その原因は我執にある。ここで、我執を凸レンズに譬える。凸レンズは物を転倒して捉えるが、平ガラスは物をそのまま捉える。我執は凸レンズのように物を転倒して捉える。坐禅は凸レンズを平ガラスに変える働きをもつ。しかし、一晩寝ると平ガラスが凸レンズに戻ってしまう。従って、一回だけでなく、毎日坐禅をする必要がある。)  ②お風呂の譬え(我々は、毎日お風呂に入る。一日分の体の垢を洗い流してくれるからである。ここで、坐禅を心のお風呂に譬える。一日生きると一日分の心の垢も溜まる。その心の垢を落とすために、毎日、心のお風呂に入る、つまり坐禅をする必要がある。)毎日坐禅を続けられるようになるためにも、長野禅会に参加して頂くように呼びかけた。
②お風呂の譬え(我々は、毎日お風呂に入る。一日分の体の垢を洗い流してくれるからである。ここで、坐禅を心のお風呂に譬える。一日生きると一日分の心の垢も溜まる。その心の垢を落とすために、毎日、心のお風呂に入る、つまり坐禅をする必要がある。)毎日坐禅を続けられるようになるためにも、長野禅会に参加して頂くように呼びかけた。(4)参加者の感想 ○坐禅でゆとりをもらった、感謝である ○初めは20分が耐えられなくなるのではないかと思ったが、良かった、ありがとうございました ○坐禅といえば、お寺・高貴な和尚さんというイメージがあったが、参加できてよかった。心を大切にするということを知った ○興味ではなく、友人に誘われてきたが、3回とも出席できてよかった、お経が気持ちよく、煩悩がでてきたら、また参加したい、その節はよろしく ○前々から興味があり、ようやく巡り合えて参加した、心の平安に良いと聞いていたが、20~25分坐れたことは有難いと思う ○腰が悪くきちんと出来なくて申し訳ない、孫の送り迎えをしているが、出席できてよかった ○坐禅に興味があり参加した、ありがとうございました ○興味があって参加した、女性の若い方がいたのは安心した ○姿勢を正しくすると、胃の痛みが治った、坐っていると体の内部が温まる、念が起こるたびに、ひとーつーと言って何とか過ごした、ありがとうございました ○坐禅に興味があった、今日の1回目の25分はあっと言う間だったが、2回目の25分は長く感じた、呼吸法を教えてもらってよかった ○心が落ち着く、お経を大きな声で唱えられてすっとした、大勢はいいだろうと感じた ●第1回目が一番よく、2・3回目の方が悪くなった、警策では背中がいたかった、今後は自分でやっていきたい ●興味本位で参加した、ひとーつーと言っても、桃太郎が出てきて困った、第1回目が一番短く感じ、2・3回目は坐禅が長く感じた ●6回の坐禅は毎回眠かった、前の2回はうまくいったが、今回は中心が坐らなかった、雑念が起こり、心が大切なのだと分かった 6.坐禅の基礎講座を終えて (1)本講座が公共機関で開催できたことは、関係者の理解もあったからで、感謝したい (2)応募者が定員枠(20)を越えて申し込み希望があったことは、嬉しいことであった (3)参加者の出席率も高く、程よい緊張感の中で、充実した禅会が実施できた (4)参加者の個々の感想や質問に丁寧に応じたので、満足して頂けたと思う (5)参加者の中には、この講座の継続を望む声も聞かれ、今後に期待がもてる (6)講師・助士も、参加者の真剣に坐禅を求める姿勢に勇気付けられた |
|
|