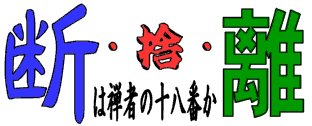
|
峰 村 鉄 男 1.求められる「断・捨・離」最近、巷ではやっている言葉の一つに「断・捨・離」がある。あり余る物に囲まれて生活している我々は、それを整理したり処分したりしなければならないのだが、なかなかうまくできないで困っている。さて、どうしたらいいのか、という悩みに対しての回答の一つが「断・捨・離」という考えと処理方法である。物が豊富で溢れている現代の、来るべくして来た結末状況のようにも思われる。 「使い捨て」といわれる時代に、なぜ物が捨てられないのかという疑問もあるが、多くの人々が悩み、それに対してテレビや本でも扱っているところをみると、なかなかの難問であるようだ。「断・捨・離」は、その言葉のように、物を断つ・捨てる・離れることであるから、結論だけみれば簡単にできそうである。しかし、実際には実行できないから悩むのである。 この悩みに対する回答は、あるテレビ番組では、「断・捨・離」するときの仕分けの基準として、どんな物に囲まれて生活をしたら、「わくわくする生活」になるのかということであり、わくわくする物は残し、そうでない物は感謝しつつ捨ててもよいということであった。物を捨てる代償として、わくわくする物に囲まれた生活というご褒美にありつける、という喜びや期待が示されているのが特色と思われる。なお、余録として整理の仕方・コツも披露されていた。 2.物への執着 上の悩みの本質は、「溜め込んだ物との別れ」にあるのだろう、と考えられる。溜め込むということは、それなりの理由のあることである。私事で恐縮であるが、私が溜め込んだ物の一つは、かつて教職に就いていた関係で、本類である。本の中身は多様であるが、それを溜め込んだきっかけを思い出してみると、先輩などから言われた「学生の時に、お金を使うのは、本を買う時か食事をする時かだ」や「教員は本屋にツケがあるのが勲章だ」という言葉だったり、「本棚をみれば、その人間の教養程度や思想傾向が分かる」などという言葉だったりする。本を読むことがあまり好きではなかった私だが、半ば他からの強制によって、半ば自分から格好をつけるために本を購入した結果、溜まっていった。そんな不純な動機で購入した本であっても、一旦、本棚に納まってしまうと、そこに居座り続け溜まってしまうのである。 そんなふうにして溜まった本は、愛着などないのであるから、処分をするのは簡単だろうと思っていた。だが、いざとなると決心が鈍り、教職を終えるまでもち続ける羽目に陥った。決心が鈍った訳の大半は、「高額なお金を掛けたのだから、勿体ない」や「神田まで出かけて買ったのだから、思い出がある」等である。いろいろと理由をつけてみるものの、結局は、物への執着なのである。「勿体ない」という気持ちや「思い出」の心は、大切な感情であるが、その心を、本の処分を避けるための隠れ蓑にしていたのではないか、と思うのである。私自身は無自覚のうちではあったが・・・。定年退職を機に多くの本を処分したが、それでもなお、決心がつかずにいる本が残っていて、女房から処分を催促される始末である。 3.心の執着 以上のようにみてくると、物への執着は心の執着と表裏一体であることが分かってくる。つまり、物を処分できないということは、物にとらわれる心の整理がつかないということである。この物へのとらわれを少なくする方法としては様々あろうが、ここでは、「かわいい子には旅をさせよ」という昔からの諺をヒントに考えてみたい。自分が大切にしている物から離れることは、わが子から離れることと似ている面があるからである。 また、わが子を執着心と読み替えることもできるのではないかとも思うからである。 さて、子どもを旅に出すというのは、親の思いの届かない所で、他人や環境の厳しさの中で甘やかさずに鍛え、心身ともに世間に通用する人間に育てたいという、親心からの期待である。しかし、手放す時は心を鬼にする、といわれる。執着の心を断つときも、わが子を旅に出すときのように、ある種の期待と心を鬼にする瞬間とが必要なのだと思う。期待としては、「放てば、手に満てり」とか「身を捨ててこそ、浮かぶ瀬もあり」などといわれるように、手離すことで却って身も心も豊かになる、という体験に基づいた快感である。では、執着心に対して心を鬼にする面は、どうであろうか。執着心はわが子のようにかわいい。かわいい執着心を旅に出すには、それなりの覚悟と時間が要る。その覚悟と時間をなかなかもてないので、たいていは、執着心を手元に置いてしまうことになる。 ところで、我々は坐禅を行としており、心の執着を少なくする訓練を日々行っている。「放つ」ことや「捨てる」ことは、正しく「我欲」というわが子同様のかわいい執着心を、旅に出す訓練に他ならない。「我欲」をできるだけ少なくするには、やはり、心を鬼にしなければできないことである。まとわりついて離れない執着心を、無理やり引き離すのであるから・・・。心を鬼にする坐禅というのが不適切ならば、勇猛心をもって坐禅をするといえばよいであろうか。かわいい「我欲」が旅に出ることの期待は、「我欲=小我(執着する心)」が「大我(執着しない心)」に成長して戻ってきてくれることである。 4.先達に学ぶ「断・捨・離」 「断・捨・離」という言葉自体はなかったとしても、同様の事態は古今東西にあったと思われる。「出家」はその典型かもしれない。「我欲」から自由になるために、世俗世間から「離れ」、家族を「捨て」、髪を「断つ」決心をし実行した先達は数知れない。そのほんの一例として、良寛を挙げてみたい。 良寛は、僧に非ず俗に非ずという立場で、住職にならず檀家をもたず、国上山腹のあばら家同様の五合庵や乙子神社に住み、「一束」の薪や「三升」の米で清貧な人生を生涯に亘って送った稀有な人である。「断・捨・離」を文字通り絵に描いたような生活であったが、心は満たされ清々としていたに違いない。そのようになれたのは、真実に生きる生得の素質に加え、坐禅等の厳しい修行で培われた堅固な信念とによって、自らを鍛え上げていった成果だとも思う。 我々は、そこまではできないが、在家として志だけはそうありたいと思う。そのために、今の自分にできる「断・捨・離」に向け、今の自分にとって簡素の象徴としての「五合庵」を、どこにどのように設定し、どのように生活すべきかを、常々考えながら生きたいものだと考える。 5.今の自分の「断・捨・離」(かわいい子には旅をさせよ) 私は、坐禅を修行のひとつとさせて頂くようになってから二十数年経つが、日常生活においては、まだまだ活かされていないことを十分自覚している。溜め込んだ本の処分などという些細な小事一つみても、執着心に惑いうろたえていることでよく分かる。物や生き方に対しての価値観の転換が不徹底であったり、特定の場での修行と日常の場での行との行き来が不十分であったりするからだと思っている。また、量から質への転換という言葉もあるが、私の場合、良質な坐禅の絶対量が不足していることも影響していると感じている。 けれども、そのことを逆に自分自身の課題や期待にして、坐禅に取り組んでいこうと思っている。坐禅を通して、「断・捨・離」を平気で実行できるようになることを、できれば、「断・捨・離」を意識せずにできるようになることを、願っている。更に進んで、この願いさえ消えてしまえば、もっといいとも感じている。「かわいい子(執着心)には旅をさせなければならない」という確信だけは、一層募ってきた。勇猛心をもって、坐禅に邁進したいものである。 |
|
|